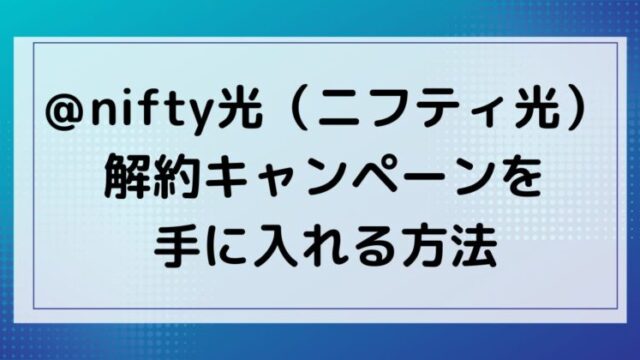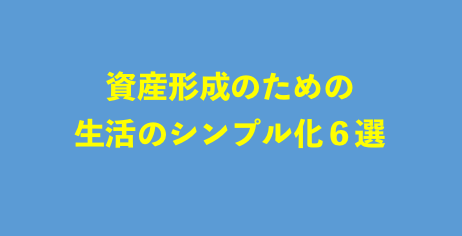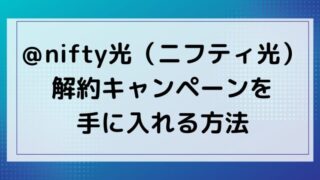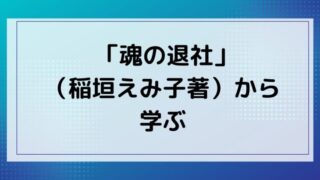生命保険をかける際の考え方について
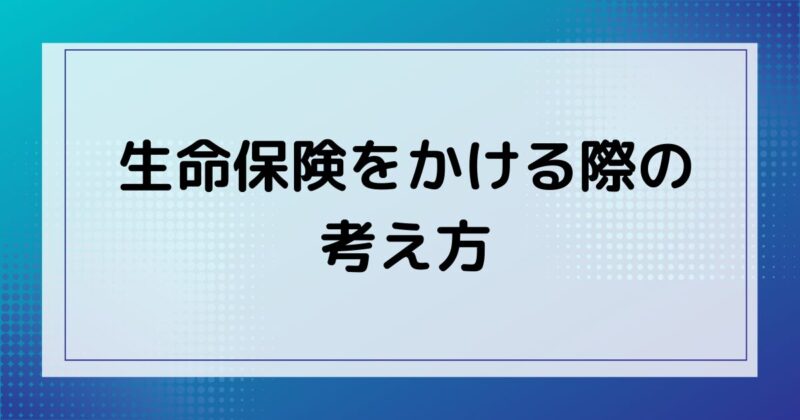
今回は、生命保険をかける際の考え方について書きたいと思います。
毎月の保険料は家計に大きな負担になることもあるので、自分にとって必要かどうかを考えることをおすすめします。
まずは結論から
今回書きたい結論は以下のとおりです。
① まず「残された家族にいくら必要か」を考える。よって、独身時代は加入不要。その分、生活防衛費への貯蓄や投資に回そう。
② 公的保険(遺族基礎年金・遺族厚生年金)、職場からの見舞金等がいくら支給されるのかを調べる。
③ ①+②でも不足する分を民間の生命保険で備える。ただし、「掛捨保険一択」。
④ 生命保険はネットの「掛捨保険」一択。民間保険の貯蓄型保険(終身・養老・変額・個人年金など)は不要。(保険担当者経由の申込みも不要。ネットで申込)
⑤ 「貯蓄は貯蓄」「保険は保険」「投資は投資」=まぜるな危険
残された家族にいくら必要かを考える
生命保険をかける目的は、「自分の収入がなくなった時に、残された家族が生活していくのに備えるため」です。
よって、現在の家族構成や年齢によって必要な金額が実際にいくら必要なのか考えてみましょう。
月々の生活代・家族の年齢によってこれからかかってくる学費・ライフイベントに備えた支出などを考えてみましょう。
なお、生命保険は「残された家族のため」になりますので、独身の方は基本不要と考えます。その分、貯蓄や投資に回すことをおすすめします。
公的年金等で支給される金額を調べる
生命保険に加入する前に、「公的年金等」で残された家族にいくら支給されるか調べてみます。
公的年金
残された遺族のための公的年金には、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」があります。
◆遺族基礎年金
受給対象となる方や具体的な金額=日本年金機構のホームページで確認
◆遺族厚生年金
受給対象となる方や具体的な金額=日本年金機構のホームページで確認
<具体的なざっくりイメージ>
月給35万円で子供1人の場合=ざっくり月額13万円程度支給(ただし、今後の法改正等で変更される可能性あり)
こうやってイメージしていくと、残された配偶者が仕事できる場合とできない場合とで、実際に必要な金額が見えてくると思います。
会社員の場合:会社からの福利厚生(見舞金等)を確認
会社員の場合、従業員本人死亡時に、会社の福利厚生制度等で数百万円の見舞金等が支給される会社もあると思いますので、まずはご自身の会社の福利厚生制度を調べてみましょう。
分からなければ、会社の総務部や人事部に問い合わせてみるのもいいでしょう。
公的年金+会社からの福利厚生(見舞金等)でも不足する分を「掛捨の生命保険」で備える
これまで述べてきた、「公的年金+会社からの見舞金等」でも不足する分を、を民間の生命保険で備えましょう。
ただし、民間の生命保険の商品は複数あり、保険担当者は「家族のためを思って」というロジックで、不必要に高い保障や、「貯蓄とセットになった商品(短期で解約すると元本割れする商品)」を提案してくると思います。
ですので、対面型の保険は不要で、「インターネットの掛捨保険」で十分です。
加入不要の代表的な保険商品(貯蓄型保険)
私自身の実体験に基づく、加入不要な保険商品と理由は以下のとおりです。
<加入不要の代表的な貯蓄型保険>
・終身保険
・養老保険
・変額保険
・個人年金保険
・似たような名称を持つ「満期になるとお金が返ってくる保険」
<加入不要な理由> 理由はいたってシンプル。
① 保障金額に対して掛金が高額だから。
② 満期前に解約すると元本割れするから。
③ 貯蓄型保険の掛金の半分近くが保険会社への手数料だから。
・保険金が保証されているというメリットはありますが、保障金額の割に、月々の掛金が高い。
・また、満期(60歳や65歳など)前に解約すると元本割れします。(元本割れしたお金は自分のお金なのに・・・)
・加えて、途中解約で元本割れするという資金拘束がある割に、資産はほとんど増えません。
・高額な掛金を拠出するくらいなら、優良なインデックスファンドへ積立投資することをおすすめします。
最後に
生命保険自体は、家族構成やライフステージなどの状況によって、場合によっては必要なもの(必ずしも絶対必要なものではない)です。
あくまでも、「必要な分に備えるため」のものであると認識し、不必要な支出を抑えて、効率的に資産形成していっていただきたいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。